こんにちは!かごパパです。
出産予定日が近づき、そわそわ、わくわく…そんな毎日を送っています。 同じ境遇のプレパパさん、プレママさん、いかがお過ごしでしょうか。
ベビー用品の準備もいよいよ大詰め。 先日、そんな話をしていた妻と、ふと顔を見合わせました。 「赤ちゃんを迎えるモノの準備は進んだけど…『お金の準備』って、何かしたけ?」
1年前に家を建てた時に一度経験したはずなのに、家族が一人増えるという大きな変化を前に、今の備えで本当に大丈夫なのかな…と、少しだけ不安がよぎったんです。
そこで今回は、僕たち夫婦がファイナンシャルプランナー(FP)さんにも相談しながら進めた「我が家の保険見直しリアル体験記」を、ありのままに記録します。
この記事が、同じように「何から始めたらいいんだろう?」と感じているご家族の、小さな道しるべになれば嬉しいです。
【全4ステップで解説】かごパパ家の保険見直し、完全ロードマップ
「保険の見直し」って、言葉だけでちょっと難しそうに感じますよね。 僕も、正直なところ少し苦手意識がありました。
でも、やるべきことを4つのステップに分けてみたら、夫婦で会話しながら、とてもシンプルに進めることができました。
ちょっと寄り道・・・【今さら聞けない】保険のキホン用語
この記事を読む上で、これだけ知っておくとスムーズです!
- 掛捨保険:貯金の機能はないけれど、安い保険料で大きな保障が手に入る保険。「お守り」のようなイメージですね。
- 積立保険:貯金の機能と保障がセットになった保険。保険料は少し高めですが、将来お金が増えて戻ってきます。「貯金箱」のイメージです。
- 定期保険:10年間や、60歳まで、といったように保障される期間が定まっている保険のこと。一般的に「掛け捨て」タイプが多いです。
- 終身保険:保障が一生涯続く保険のこと。「積立」タイプが多く、資産形成の役割も持ちます。
- 学資保険:子どもの教育資金を準備するための**「積立保険」の一種です。
- FP:ファイナンシャルプランナーの略。家計や保険、資産運用など、お金に関する幅広い相談に乗ってくれる専門家のことです。
- 団信: 団体信用生命保険の略。住宅ローンの契約者が亡くなった場合などに、ローンの残りを全額返済してくれる生命保険です。
ステップ1:【現状把握】まずは「我が家」を知ることから
最初の一歩は、今の僕たちがどんな保険に入っているのかを正確に知ることでした。
我が家の「見直し前」の保険と、その課題
ちなみに、見直し前の我が家の保険はこんな状況でした。
- 夫:かんぽ生命。満期でお金は戻ってくるけど、その後の保障がなくなってしまうタイプ。
- 妻:県民共済。掛け金が安く、割戻金があるのは嬉しいけど、60歳で満期になってしまうのと、短期入院への保障が少し弱いのが気になっていました。
「このままで、子どもが生まれた後の生活を本当に守れるんだろうか?」 これが、僕たちの見直しのスタート地点でした。
やったこと
- 住宅ローンの団信を再確認
- 夫婦それぞれの保険証券をテーブルに並べる
- 保障の重複がないか、逆に足りない部分はないかをチェック
ステップ2:【未来の安心設計】家族を守るために、いくら必要?
現状がわかったら、次は「家族の未来」のために、どんな備えがあれば安心できるかをシミュレーションします。
これは、決してネガティブな話ではありません。 これから生まれてくる我が子への「最大の愛情表現のひとつ」だと、僕たち夫婦は考えました。
- パパにもしものことがあったら
- 妻にもしものことがあったら
一度、こうして具体的に考えてみることで、「これくらいの備えがあれば、きっと大丈夫だね」と夫婦で笑いあえる、安心の着地点が見えてきました。
ステップ3:【方針決め】「我が家の価値観」を話し合う時間
必要な金額がイメージできたら、次は「どんなことを大切にしたいか」という、我が家の方針を決めます。ここが一番、夫婦の価値観をすり合わせる大切な時間でした。
- 我が家のルール①:過度に心配しすぎない
- 我が家のルール②:児童手当は「未来」のための贈り物
- 【コラム】家を建てたからこそ気づけた、もう一つの「備え」
ステップ4:【我が家の結論】FPさんと見つけた、わが家だけの正解

夫婦である程度の方向性が固まった後、僕たちは専門家であるFPさんに相談し、考えを整理するのを手伝ってもらいました。そしてたどり着いたのが、保険を「保障」と「資産形成」の役割に分けて考える方法です。
1. もしもの時の「保障」を固める
まずは、病気やケガ、そして万が一の時のための、純粋な「お守り」です。
- 医療保険(掛け捨て)※病気や怪我への備え
└妻:月々2,762円
└夫:月々2,756円
- 死亡保険(掛け捨て)※夫のみ
└夫:月々2,756円
【保険の選択理由】
僕にだけ死亡保険を掛け捨てがある理由は僕に万が一のことがあった場合、住宅ローンは無くなりますが、妻と子どもがその後も安心して暮らしていくための「生活費」はどうしても必要です。その備えとして、手頃な掛け捨ての死亡保険を追加しました。
2. 未来のための「資産形成」を進める
次に、子どもの教育費や自分たちの老後資金を兼ねた、貯蓄。ここが将来の学費や家の修繕積立に備える部分です
- 死亡保険(積立)
└妻:月々5,000円
└夫:月々10,000円
【コラム】ところで、FPさんってどうやって見つけるの?
僕の場合は、家を建てた時のご縁で担当の方に相談できましたが、「うちはどうしたら…?」と思う方もいらっしゃいますよね。
そこで、僕なりに調べてみたところ、FPさんに相談するには、主にこんな方法があるようです。
- パターン1:街の保険相談ショップ(無料) ショッピングモールなどで見かける「来店型の保険ショップ」のような場所です。。複数の保険会社の商品を比較しながら、中立的な立場でアドバイスをくれるのが特徴のようです。相談は無料で、気軽に予約できるみたいですね。
- パターン2:銀行などの金融機関 いつも使っている銀行の窓口でも、保険や資産運用の相談に乗ってくれるようです。安心感がありますね。
- パターン3:独立系FPさんを探す 特定の会社に所属せず、個人で活動されているFPさんもいらっしゃるようです。こちらは相談が有料の場合もあるようですが、より専門的なアドバイスがもらえるのかもしれません。
自分に合った方法で、一度プロに相談してみるのは、とても良い選択肢だと思います!
「学資保険」を選ばなかった理由。 我が家なりの、お金の考え方。
「子どもの教育費」と聞いて、真っ先に思い浮かぶのが「学資保険」ですよね。 僕たちも、もちろん考えました。
でも、FPさんともたくさん話した結果、我が家は「学資保険」という名前の商品ではなく、ステップ4で紹介した「積立型の保険」で準備することに決めました。
一番の理由は、教育費にも、他のことにも使える「自由度の高さ」です。 これからの時代、どんなふうにお金の価値が変わっていくか分かりません。だからこそ、柔軟に使える形で備えておきたい、というのが僕たち夫婦の結論でした。
そして何より、この積立保険には「死亡保障」がついています。もし運用中に親に万が一のことがあっても、まとまったお金が家族に残る。この「守り」と「攻め(資産形成)」のバランスが、学資保険代わりとして最適だと判断しました。
この積立保険、30年間続けた場合のシミュレーションも見せてもらいました。 (※もちろん、未来を保証するものではありません)
- 妻:支払総額 180万円 → 30年後の解約時の想定額 280万円
- 夫:支払総額 360万円 → 30年後の解約時の想定額 630万円
保障を備えながら、未来のために資産を育てていく。この形が、今の我が家には一番しっくりきています。
※ご注意: 上記のシミュレーションは、運用実績や為替の影響によって変動する可能性があります。元本割れのリスクや、途中解約時の返戻金が支払総額を下回るケースもあるため、加入の際は必ず最新の設計書をご確認ください。
まとめ
ここまで、僕たち夫婦のリアルな保険見直しの記録を読んでいただき、ありがとうございました。
正直、少し面倒に感じる作業かもしれません。 でも、もうすぐ会える我が子のことを想いながら夫婦で話す時間は、とても温かくて、家族の絆が深まる大切な時間になりました。
子どもが生まれる前の、少しだけ落ち着いた時間がある「今」だからこそ、未来の話をしてみませんか。
この記事が、あなたの家族の、小さなきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
👇 お金の準備ができたら、次はパパの出番!「出生届・児童手当」の手続きリストはこちら


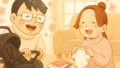
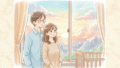
コメント